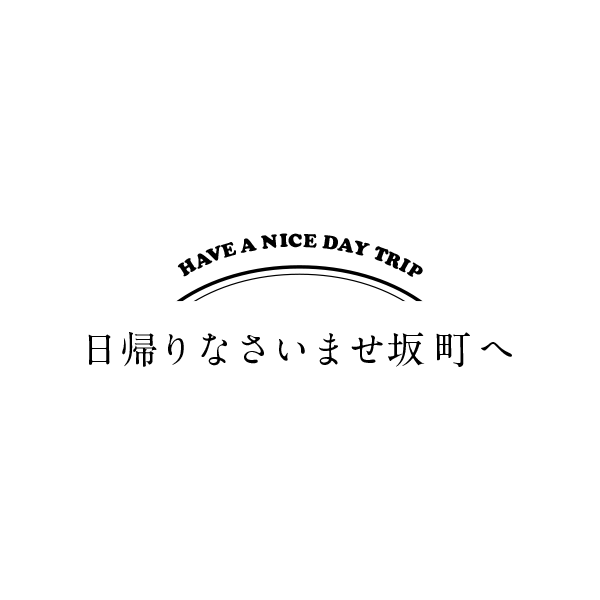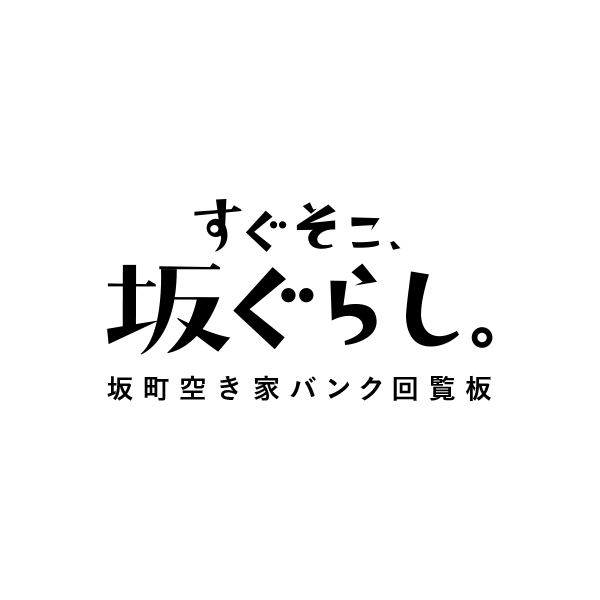令和7年度教育行政方針
1 はじめに
グローバル化や技術革新の急速な進展、気候変動など、社会は依然として変化の速度を増しており、予測が困難な状況が続いています。このような時代の中で、学校教育には一人一人の子どもたちに、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となるために必要な資質や能力を育成することが求められています。
国では、「※GIGAスクール構想」の実現に向けて、ICT環境がこれからの学校教育を支えることを前提に、今後の学校教育の在り方について検討されています。
坂町においても、国の動向を踏まえ、ICT環境の効果的利用を基盤とした教育活動をさらに進化させ、子どもたちの可能性を最大限に引き出す教育を推進します。子どもたちの主体的・対話的で深い学びの実現に向け、デジタル教材の効果的な活用等を通じて、子どもたちを誰一人取り残すことなく育成する「個別最適な学び」と子どもたちの多様な個性を最大限に生かす「協働的な学び」を一体的に充実させる取組を推進してまいります。
また、情報活用能力の育成のみならず、情報モラルや情報セキュリティに関する教育を充実させ、情報社会で適切に活動するための基盤を育成します。
これらの取り組みを通じて、変化の激しい社会を生き抜く力、自ら学び続ける力、そして他者と協働して新たな価値を創造する力を育み、子どもたちの未来を拓いていきます。
さらには、人生100年時代の到来など社会の変化や課題を踏まえた新しい時代を迎える中、生涯学習の重要性は一層高まっており、学校教育での学びを生かし、町民一人一人が生涯を通して学ぶことのできる環境の整備、多様な学習機会の提供等、生涯学習の理念を踏まえた総合的な政策を推進してまいります。
また、令和6年度におきましては、多くの行事やイベントを例年通り開催いたしました。参加者はコロナ前の水準にはまだ戻っておりませんが、少しずつ回復傾向にあります。
引き続き、令和7年度においても、行事やイベント等の目的や効果を再検証し、町民の皆様に喜んで参加していただけるよう柔軟かつきめ細やかに施策を展開してまいります。
坂町教育委員会といたしましては、「町長施政方針」及び「坂町長期総合計画」等に基づき、また「総合教育会議」の趣旨を踏まえ、町長部局と一体となって、効果的な教育行政を推進してまいります。
※GIGAスクール構想
1人1台端末(タブレット)を実現し、子どもたちの資質・能力を一層育成するICT環境の構築
2 学校教育
(1)「礼節」を基本とした教育の推進
一人一人の子どもたちが、自らを律しつつ他者と協調し、思いやりや感動する心を育みながら、「礼節」をわきまえた行為へと深めていく教育を推進してまいります。
時と場所、場合に応じた適切な挨拶や言葉遣いのできる「礼儀」と、自分自身の立場をわきまえ、よく考えて行動し、生活することのできる「節度」を一体として捉え、全ての教育活動を通して取り組んでまいります。
(2)確かな学力の向上
これからの社会を主体的・創造的に生き抜いていくために、児童生徒一人一人に基礎的・基本的な内容の定着を図り、自ら学び、自ら考え、主体的に判断・行動し、よりよく問題を解決する資質や能力を育成してまいります。
これにより、各教科に関する学力を結びつけ、SDGsによって、環境配慮への関心が高まる中で、地球規模の課題としての環境問題の解決に繋がる取組(エコフレンドリー)を理解し、実践することや、現代社会における、選挙権年齢の引下げや金融環境の大きな変化によるリスクやトラブル等の諸課題に対応する知識や判断力の習得を図ってまいります。
(3)体力・運動能力の向上
体力は人間の発達・成長を支え、創造的な活動をするために大切な役割を果たすことから、将来を担う児童生徒の体力を向上させることや、食育の推進については、生涯にわたって、健全な心と身体を培い豊かな人間性を育む基礎となり、坂町の未来の発展のためにも重要であると考えます。
今後も、各学校の実態を踏まえ、「体力つくり改善計画」を作成し、体育・保健体育の授業をはじめ、学校教育活動全体を通して、体力・運動能力の更なる向上に努めます。
また、給食や様々な経験を通じて、食育についての学習機会の充実を図り、望ましい食習慣を形成してまいります。
これにより、児童生徒が心身ともに健やかで安全に成長していくことができる取組を推進してまいります。
(4)ICT教育の推進
社会全体のデジタル化が推進される中、学校においても学習指導要領に示された資質・能力の育成を着実に進めることが重要です。育成に当たっては、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実に努め、授業での対話場面を重視し、「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業改善を進めるとともに、学校におけるICT環境を最大限活用し、電子黒板やデジタル教科書等の新たな教材や学習活動等も積極的に取り入れつつ、情報モラル教育を含めたICT教育を推進してまいります。
(5)平和教育の推進
平和教育においては、自他の生命と人間の尊厳を尊重する心を育むことを根幹とし、戦争の悲惨さや平和の尊さを多角的に学ぶことが重要です。令和7年度は、沖縄県内自治体との交流事業を通じ、中学生同士が歴史や文化、そして平和への想いを共有する機会を設けます。この交流などを通して、児童生徒が過去の出来事を深く理解し、未来に向けて平和を希求する心を育めるよう、取り組んでまいります。
(6)防災教育の推進
平成30年7月豪雨災害の経験や教訓を生かした防災教育を推進し、生涯にわたる防災対応能力の基礎を育成し、復興に向けて心身ともにたくましく生き抜く力を育む防災教育を推進してまいります。
推進に当たっては、教育活動全体を通して、自然災害についての理解を深め、「待つな!迷うな!逃げろ!」を合言葉とし、災害時に的確な思考・判断に基づく適切な意思決定や行動選択ができる力を育成します。また、自他の生命を尊重する心を育て、学校・家庭・地域の安全活動に進んで参加・協力・貢献できるような資質や能力を養い、主体的に行動し防災に対応することのできる人材を育成してまいります。
(7)特別支援教育の推進
児童生徒の自立と社会参加を一層推進していくために、児童生徒一人一人の教育的ニーズを的確に把握し、ユニバーサルデザインに配慮した教育環境を充実させるとともに、適切な指導や支援を行ってまいります。
このため、各学校で「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」を作成し、効果的に活用するとともに、「※特別支援教育コーディネーター」を中心に校内体制を整え、関係機関等との連携を積極的に進め、研修の充実や指導内容、指導方法の改善を進めてまいります。
※特別支援教育コーディネーター
学校内の関係者や外部の関係者との連絡調整役、保護者に対する相談窓口、担任への支援、校内委員会の運営や推進役
(8)グローバル人材の育成
グローバル化が進展する中、多様化する価値観や世界規模の課題に対応する姿勢を育み、持続可能な社会の創り手となるために必要な資質や能力を身に付けることが求められています。
坂町で育ったことに誇りをもち、胸を張って坂町を語り、国際社会で活躍できるよう、語学力やコミュニケーション能力を育み、自らの考えや意見を伝え、主体性や創造性、責任感、チャレンジ精神をもって行動できる能力や態度を育成します。また、異なる文化や価値観を理解し、国際社会の平和や発展に貢献する人材を育成してまいります。
(9)生徒指導体制の確立
児童生徒を取り巻く社会環境が大きく変化する今日、問題行動の未然防止や早期発見・早期解決と健全育成を一体的に捉え、児童生徒一人一人の規範意識を高め、自己を律し社会的自立を促進する生徒指導体制の確立を図ってまいります。
また、学校・家庭・地域・関係機関等が互いに連携し、それぞれの教育力を生かした開かれた生徒指導を推進し、校内における教育相談体制の充実に努めてまいります。
とりわけ、不登校の増加に対しては、SSR(スペシャルサポートルーム)等を活用しながら、支援の基本的な考え方について共通認識を持ち、不登校児童生徒の社会的自立に向け、支援の一層の充実を図ってまいります。また、いじめ問題については、「どの子にも、どの学校にも起こりうる問題」として認識し、いじめの未然防止に努め、いじめが生じた際には、迅速な対応、悪化の防止、真の解決に結びつけるために、学校と教育委員会が家庭と連携し一体となって適切に対応してまいります。
(10)保育園・こども園・小・中学校における連携・接続の推進
町内の保育園・認定こども園、小学校、中学校間が円滑に連携・接続しながら子どもの発達や成長段階にあわせた教育の連続性、一貫性を確保し、子どもに対して体系的な教育が組織的に行われることが重要です。
このため、就学前後の架け橋期の学びと育ちの連続性を重視し、保育園・認定こども園と小学校が互いの保育・教育を理解し、幼児教育で培われた主体性や学びに向かう力を小学校以降の教育へ円滑につなぐことで、見通しをもって、子どもの育ちと学びを連続させていく連携体制の構築と教育内容の充実を図ってまいります。
また、小・中学校では9年間の教育課程を系統的、継続的な一つのまとまりとして捉え、学校間の円滑な連携・接続を確保し、心身ともに健康で、子どもたちの発達段階に応じた「生きる力」を育成してまいります。
(11)「地域とともにある学校づくり」の推進
学校と地域が学校の目標を共有し、一体となって地域の子どもたちを育んでいくことは、子どもの豊かな育ちを確保し、地域の絆を強め、地域づくりの担い手を育てていくことにもつながります。
このため、「坂町の教育を考える会」の方針に基づいて、町内各学校区において、地域住民や保護者等が学校運営に参画する学校運営協議会(コミュニティ・スクール)を活用し、学校と地域が連携・協働しながら一体となって子どもたちの成長を支える「地域とともにある学校づくり」を推進してまいります。
また、中学校の部活動においては、学校主体で教育の一環として地域とともに盛り上げていけるよう、部活動指導員の配置に配慮しつつ関係機関と連携してまいります。
(12)安全・安心な学校環境の整備
学校施設は、未来を担う子どもたちが集い、生き生きと学び、生活をする場であるとともに、地域住民にとっては生涯にわたる学習、文化、スポーツなどの活動の場であり、災害時等には避難場所・避難所として役割を果たす重要な施設です。
引き続き、学校施設の改修整備は、安全で安心して学ぶことができる施設及び避難場所・避難所としての維持管理が重要であり、老朽化対策として策定した「長寿命化計画」に基づき、効果的・効率的に長寿命化を図り、良好な状態の維持や安全性の確保及び環境問題を考慮した学校施設整備に努めてまいります。
また、教職員の長時間勤務課題の解決に向けて、児童生徒の出欠や成績の管理を行う校務支援システムの運用等により、教員が子どもと向き合う時間を確保し、健康でいきいきとやりがいをもって勤務できる環境づくりを推進してまいります。
3 生涯学習
(1)生涯学習社会の推進
社会の急激な変化を背景に、価値観の多様化する中で長い人生を生き生きと生きるため、あらゆる世代、すべての生活の場における生涯にわたっての学習が重視されています。
そのため、町民一人一人が生涯を通して学ぶことのできる環境の整備、多様な学習機会の提供、学習した成果が適切に評価されるための仕組みづくりなど、生涯学習社会の実現を目指した取組を推進してまいります。
(2)生涯学習環境の整備
学習活動のさらなる充実を図るため、学習意欲をもつ誰もが、それぞれのライフスタイルに合わせて、いつでも、どこでも、気軽に学べる環境づくりを支援してまいります。
町民センターや図書館などの公共施設が町民の身近な学習拠点や交流の場として活用されるように、多様化・高度化する学習内容や学習方法に対応してまいります。また、小・中学校を含めた施設間の連携、施設・設備等の充実を図り、活用の利便性に努めてまいります。
町民交流センターは、令和6年度に「シモハナHall」に愛称を変更し新たな一歩を踏み出しました。今後も、町民に親しまれ、スポーツ・文化活動の交流拠点として活用されるよう関係機関等とも協力し、利用促進に努めるとともに、防災の拠点として、施設の適切な点検及び維持管理に努めてまいります。
(3)生涯学習推進体制の確立
社会の変化や町民の学習ニーズに応じた学習機会の提供や、学習活動をより豊かで魅力あるものとするため、中心的役割を担う指導者及びコーディネーターの確保と育成に努め、生涯学習を推進する体制の確立に努めてまいります。
また、講座参加者の安全・安心を確保し、継続して活動ができるよう自主グループの育成や生涯学習に関係する機関・団体間の連携・協力体制の構築を図ってまいります。
(4)図書館運営の充実
図書館は、地域の情報の拠点としての役割を果たすため、蔵書・資料などの計画的な収集・整備に努め、誰もが知識や情報を得ることができる環境を整えてまいります。
また、学校、公民館等、関連施設と連携し、町内全域で質の高い図書館サービスが提供できるよう資質の向上を図り、図書館機能を活用した生涯学習機会の提供と充実に努めてまいります。
子どもの読書活動については、「坂町子ども読書活動推進計画」に基づき、家庭・地域・学校など社会全体で推進してまいります。事業につきましては、読み聞かせや図書館まつりを開催して、図書館に興味を持っていただけるような取組をしてまいります。
なお、「坂町子ども読書活動推進計画(第三次計画)」の最終年度にあたるため、令和3年度以降の取組みに係る成果と課題を検証することにより、次期につなげてまいります。
(5)生涯スポーツ社会の振興
町民の誰もが生涯を通じていつでも身近にスポーツに親しむことができる環境を整備し、幸福で豊かな生活を営むことができる生涯スポーツ社会の実現を目指してまいります。
推進に当たっては、坂町体育協会やスポーツ推進委員協議会等の関係機関と連携・協力し、「坂町悠々健康ウオーキング大会」をはじめとする各種スポーツ大会や主催事業を開催し、町民にスポーツ活動を通して、心身の健全な発達や体力増進・健康維持の機会の充実を図ってまいります。
また、令和3年度に坂町と中国電力ラグビー部が締結した連携協力に関する協定を基に、同ラグビー部と地域の繋がりを密にし、応援していくことで町民の一体感による愛着や誇りを醸成し、坂町だからこそ体感できる取組を目指してまいります。
(6)芸術・文化活動の振興
芸術・文化活動は、人々に感動や生きる喜びをもたらし、暮らしに潤いと活力を満たす大きな力となることから、芸術・文化を大切にする社会の実現を目指してまいります。
町民センターをはじめ、公共施設における自主グループや芸術・文化団体の育成と支援を継続し、「坂町歌」「坂町音頭」の普及と振興に努め、地域に根ざした芸術・文化活動を推進してまいります。
また、文化協会・関係機関及び団体等と連携し、芸術・文化活動の活性化が図られるよう、情報の提供や発表の場、参加する機会の拡充に努めてまいります。
更には、令和7年度は、町制施行75周年の節目の年であることから、現在、町民センターに展示しております六角御輿と坂町音頭を軸として、5月に開催される「ひろしまフラワーフェスティバル」のパレードに出場することとしています。
中学生が御輿を担ぐことによって、伝統を復活させ、後世に引き継いでいくことにより、郷土への誇りや愛着が醸成されるものと考えております。
(7)青少年の健全育成
青少年の健全な育成は、青少年が、豊かな人間性を育み、心身ともに健やかに成長するとともに、社会とのかかわりを自覚しながら、次代の社会の担い手として自立することを目指してまいります。
このため、青少年育成坂町民会議や学校等と連携し、「あいさつ運動」や「道徳作文」、「青少年の主張」などへの参加を促進し、あらゆる機会を捉えて、他人を思いやる心や善悪の判断などの基本的倫理観を養い、社会的なマナーを身につける等の健全な育成に努めてまいります。
(8)「※放課後子どもプラン」の推進
子どもたちが放課後や週末の自由な時間を安全で安心して活動できる拠点として、「放課後子ども教室」や「子どもチャレンジ講座」の充実に努め、地域全体で子どもを守り育てる意識の啓発を図り、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性の涵養を目指してまいります。
現在「留守家庭児童会」は、坂・横浜・小屋浦の全ての地区で待機児童も無く、全学年の受け入れを行っており、令和6年度からは長期休業中のみの受け入れも開始いたしました。今後も「放課後子ども教室」と連携して、安全への配慮を徹底しながら、放課後の適切な遊びや生活の場を提供し、子どもたちの健全育成と子育て支援の充実に努めてまいります。
※放課後子どもプラン
地域社会の中で、放課後等に子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため実施する、総合的な放課後の取り組み(放課後子ども教室、留守家庭児童会等)
(9)町史の普及・活用の促進
坂町におきましては、多くの先人が培われてきた貴重な文化財が多数存在しております。
町民の歴史や文化に対する関心・意欲を高め、先人が築いた歴史や文化を次世代に継承するため、引き続き坂町史の普及・啓発活動に努めてまいります。
これまで保管している民具等の資料を展示するための「(仮称)ふるさと資料館」を整備し、完了した際には、ウオーキングコースに取り入れ、子どもたちや地域の皆様をはじめ、町内外の多くの方々にご覧いただくことで、貴重な歴史・文化を後世に伝えてまいります。
また、令和5年度に制作いたしました、畝為吉氏の功績を称える偉人マンガを引き続き4年生に配布して学習活動に利用するなど、郷土愛の醸成に努めてまいります。
(10)国際交流の推進
国際化が進展する中、青少年自らが国際社会の一員であることを自覚し、異なる文化や歴史に立脚する人々と共生していくことが求められているため、外国人講師を招いての英会話教室や料理教室等を開催し、異国文化に触れる機会を提供してまいります。
また、「坂町海外研修青少年対象事業」につきましては、長引く円安の影響による渡航費用の高騰により、断念せざるを得ない状況となっております。しかしながら、円安の解消等、安全・安心に渡航できるような状況になった際には、再開できるよう準備をしてまいります。
4 おわりに
坂町教育委員会といたしましては、「夢や希望を育み、絆をつくる人づくり」を基本目標とし、子どもたち一人一人の能力や個性を伸ばし、新たな時代を豊かに生き抜く力を育成する質の高い教育を推進し、学校・家庭・地域が一体となって子どもたちを育む「地域とともにある学校づくり」の充実に努めてまいります。
また、町民の皆様が生涯を通じて健やかに充実した生活を送ることができるよう、文化に親しみ、スポーツを楽しむための環境づくりに努め、「社会が人を育み、人が社会をつくる」好循環と生涯学習社会の実現を目指した効果的な取組を進めてまいります。
厳しい財政状況の中、町当局の教育行政に対する温かいご支援に心から感謝申し上げるとともに、その期待に応えるため、より一層努力し、坂町教育の向上及び発展のために邁進してまいります。
今後とも議会の皆様並びに町民の皆様のご理解とご協力をお願いいたしまして「教育行政方針」とします。